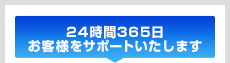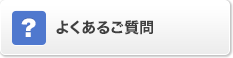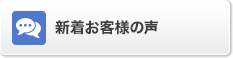作成者アーカイブ: administrator

代・
ラインを引き直したい
アスファルトの種類と機能性を公道・駐車場の施工事例から解説

公道の舗装素材に用いられるアスファルトは、その機能性の高さから道路だけでなく住宅の駐車場造りや外構工事などでも使われています。アスファルトは、異なる構造や混合物を用いて舗装すると、特徴や外観を大きく変えることができます。
本記事では、アスファルトの様々な施工事例をご紹介します。アスファルト舗装の目的は依頼主の希望によってさまざまです。アスファルト舗装をお考えの方がいましたら、種類と機能性を生かして舗装する方法を、施工事例を通して探してみてください。
目次
アスファルト舗装の施工事例:公道編
まずは公道におけるアスファルト舗装の施行例をご紹介します。
一般住宅の駐車場を舗装したいから道路の舗装事例は関係ない、と思う方もいるかもしれませんが、道路の舗装方法はさまざまで、一般家庭の駐車場でも取り入れると効果的な方法もあります。
道路ではどのような舗装がされているのか、4つの舗装事例に注目して見てみましょう。
アスファルト舗装で快適な走行
公道で一般的に使用されるアスファルト舗装の材料は「密粒度アスファルト混合物」と呼ばれます。
密粒度アスファルト混合物には、以下の利点があります。
- ・施工が簡単
- ・修繕も容易
- ・排水性が良い
- ・車の走行性が高い
施工・修繕が簡単にできるので、公共の場であり多くの人が必要とする道路には適切です。また、排水性が高いのでスリップが起こりにくくなり、事故やケガを防ぐのにも適しています。走行性が高いので、車通りの多い場所でも車の走行音が気になりにくく、快適に運転することもできます。
カラーアスファルト舗装で歩行者の安全を確保
一般的なアスファルト舗装はコンクリート舗装のようにカラーバリエーションが多様ではなく、ほとんどが黒や暗いグレーであるという理由から、無機質で景観が良くないと思われがちです。また、そのくらい色により視認性が良くないことが問題になることもあるようです。そのような問題を解決するのが「カラーアスファルト」です。
カラーアスファルトとは色の着いたアスファルトのことで、様々な樹脂類を材料に加えることで着色されます。色付けされたアスファルトを使うことで、街の景色との調和が容易になるほか、歩道などで安全を誘導するなどの機能も持ち合わせています。歩道では、歩行車の安全を高めるため樹脂モルタル舗装が使われることが多いようです。
雨天時でも安全な走行ができる排水性舗装・浸水性舗装
一般的なアスファルト舗装は高い排水性を持つ一方で、路面上で水が排水されるため、ハイドロプレーニング現象が起きてしまう可能性があります。交通量が多く雨による事故が危ぶまれるような道路では、「排水性舗装」や「透水性舗装」といったような、路面上に水分がたまらない排水機能を持った舗装方法が用いられます。
【構造の違い】
一般的に用いられる密粒度アスファルトと排水性・透水性アスファルトの違いは、最上層に敷く材料です。密粒度アスファルトは不透水な素材を最上層に使用するため、雨水を吸収することができません。
しかし、排水性舗装では不透水層の上にポーラスアスファルトという不透水層よりも密度の低い素材が使われています。ポーラスアスファルトは雨水をアスファルト表面から路盤に取り込むので、雨水が道路の表面を流れることなく、スリップを防ぐことができるのです。
透水性舗装では、不透水層は使用せず、ポーラスアスファルトのみを表層に使います。これにより、透水性舗装は雨水を路床間まで吸収することができるのです。
雪が積もる地域では砕石マスチック舗装
雪がよく積もる地域では、「砕石マスチック舗装」という方法が多く取り入れられます。
砕石マスチック舗装とは、粗骨材と接着剤を多く使用しているアスファルト合材のことを指します。砕石マスチック舗装をすることで、道路が雪に覆われたり凍ったりしやすい地域でも滑りにくくなる効果があります。材料の配合加減により水密性が高いです。また、摩耗に強くたわみ・ひび割れが起こりにくいという特徴も持ち合わせているので、寒い地域だけでなく、一般道路の中でも特に多く利用される幹線道路にも使われるようです。
アスファルト舗装の施工事例:駐車場編

次に、一般家庭や有料駐車場でも取り入れられているようなアスファルト舗装の施行例をご紹介します。
大きなリフォームから、DIYでの修繕工事まで、さまざまな規模の施工事例をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
お庭を駐車場にリフォーム
車を使用する機会は多く、子供がいる家庭では、子供が大人に近づくにつれ車の台数が増えることもあります。車が増えるとより広い駐車場が必要になりますので、お庭を駐車場に変えようと考える方もいるかと思います。
一般家庭や店舗で駐車場を作る場合は、お庭からのリフォームであるかどうかにかかわらず、景観を気にされる方が多いと思います。ご自宅や近隣住宅にマッチした景観の駐車場にしたい、通る人の目を引くようなおしゃれな駐車場にしたいなど、多様な意見があるでしょう。
無機質な印象になりやすいアスファルト舗装ですが、少し工夫をすることでデザイン性の高い駐車場を作ることができます。例えば、アスファルトにタイルを組み合わせることで、おしゃれ度が一気に上がります。また、アスファルト意外にタイルなど明るめの素材を使えば、色のコントラストを楽しむこともできます。さらには、マットスプレーで色を使って模様をつけることも可能です。好きな模様を描けば、オンリーワンな駐車場が出来上がります。
空き地を駐車場にして活用
使用していない土地がある場合には、その空地を有効活用して駐車場を造るケースも多々見られます。
空き地をアスファルト舗装すると得られる効果としては、土や砂利の場合比べて雑草が生えにくくなり、手入れをする手間が省けることが第一に挙げられます。
また、排水性に優れたアスファルトは水たまりを作りにくいので、その土地を雨の日に使用するときにも安心です。すでに空き地を駐車場として貸している方にも、アスファルト舗装のメリットはあります。土や砂利の駐車場だと車に土が付着したり砂利が車体に当たり傷をつけてしまったりといったことが考えられますが、アスファルト舗装をして車止めなどを設置した駐車場ならそのような心配はありません。きれいに舗装をすることで、利用者の増加も見込めるでしょう。
傷んだ駐車場をDiYで補修
アスファルトがいくら耐久性に優れ強度があるといっても、年々劣化し傷むことや亀裂ができることはあります。随分と劣化している状態ならば業者に依頼して補修してもらう方がよいでしょう。しかし、小さな亀裂などならご自分で修理をすることが可能です。
ひび割れ部分などの小さな箇所の補修には、アスファルト補修材が使われるようです。市販で売られているものもあるので、手軽に取り入れられる補修方法といえそうです。
ラインが薄くなってきたときには、自分でライン引きをすることも可能です。白いラインを引くには、長めのスケールとチョーク、白い塗料、マスキングテープ、ローラーを用意します。チョークで下描きをし、マスキングテープで囲った部分にローラーで塗料を塗ることで、簡単に白線を描くことができるのです。
このように、アスファルトはDIYでの補修が可能なので、メンテナンスを自分で行うことができ、管理費用を抑えることができます。高い費用を払うことなく修繕することができるアスファルト舗装なら、劣化したときのことを考えても翁不安を抱えなくて済みそうです。
まとめ
さまざまなアスファルト舗装の施工事例をご紹介しました。重要なポイントをおさらいしてみましょう。
● アスファルト舗装には多様な材料が使われている
● 地域性や舗装目的に合った材料を使用することができる
● 空き地やお庭を有効活用して駐車場を作ることが可能
● タイルなど他の素材を組み合わせればおしゃれな駐車場に
● 小さな劣化ならDIYで修繕することも可能
これらを参照して、よりよい駐車場造りをしてみてはいかがでしょうか。

代・
ラインを引き直したい
アスファルト舗装の手順や工程を間違えると耐久年数が短くなります

地面の舗装工事には、一般的なコンクリート舗装のほかに、道路によく見るアスファルトを使った方法もあります。
水はけが良く滑りにくいため駐車場の舗装などに適するアスファルトですが、ただしい手順を踏んで施工を行わないとうまく性能を発揮できず、耐久年数が短くなってしまう可能性があります。
ここでは、アスファルトの舗装工事がどのような工程を経て行われるのかを段階に分けて解説いたします。
またアスファルト舗装工事に使用される重機や専用車両といった機材から、舗装の品質を担保する品質管理試験の内容など、施工の際に知っておくと便利な知識をご紹介していきます。
基本的なアスファルト舗装の手順と工程の意味
アスファルトによる舗装工事には、大まかにわけて下から『路床』『下層路盤』『上層路盤』『基層』『表層』の5つの工程があります。
ここでは、それぞれの工程の内容と、それによって得られる効果を合わせてご説明していきます。
アスファルト舗装工事の工程1 路床
舗装の最下層、『路床』と呼ばれる部分の敷設です。
路床は路面から約1メートルの深さに位置するため、まずはそこまで掘り下げる掘削作業から始めます。
掘り終えた溝に砂を敷き詰め、舗装の土台を構築していきます。舗装面にかかる荷重は最終的にこの路床で受け止めることになるため、路床が脆弱だと地盤沈下などのトラブルが発生する可能性があります。
地盤があまりにも脆弱な場合、鉄筋を埋めるなどして地盤強化の施工を行うこともあります。
アスファルト舗装工事の工程2 下層路盤
『路盤』は舗装の中間地点を支える部分のことで、上層と下層にわかれてそれぞれ荷重や衝撃を分散させる役割を持っています。
敷設を終えた路床の上に、砕石や砂利などを敷き詰めていきます。
下層路盤に用いる砕石は、荷重をしっかり受け止めるために比較的大粒なものが多いと言われています。
アスファルト舗装工事の工程3 上層路盤
路盤の上層にも同様に砕石を敷いていきます。
上層路盤はすぐ上の基盤から伝わってくる荷重を均一に受け止めて下層へ分散させる役割を持つため、敷かれる砕石は比較的小粒なものが多いです。
また荷重分散のロスを出来る限り減らすために、均一な大きさに整えられた砕石が用いられます。敷き終えた砕石は、ロードローラーなどで踏み固めていきます。
規定の密度になるまでしっかりと圧縮することで、強固な路盤を得ることができます。
アスファルト舗装工事の工程4 基層
路盤の上に敷かれる層で、ここからの材料がアスファルトになります。
基盤は上層路盤と上部の表層との間でクッションとなる層のため、使用されるアスファルトは柔軟性に富んだものになります。
ならされているとはいえ、ごつごつとした砕石の上層路面を柔らかいアスファルトで覆い、表層との密着性を高めるはたらきをしています。
アスファルト舗装工事の工程5 表層
舗装の最上部、普段目にするアスファルトの層を表層と呼びます。
基層によって支えられている表層には、柔軟性よりも耐久性を重視したアスファルトが用いられます。
路面にかかる荷重と衝撃を分散して基層へと伝え、路面を平坦に保つことで快適に通行ができるようにしています。
また路面に水が溜まらないように排水溝に向かって傾斜を付ける『余盛り』と呼ばれる作業もここで行います。
余盛りが済んだら、仕上げとして敷き詰めたアスファルトをローラー等で踏み固める『転圧』作業を行います。敷かれたばかりのアスファルトは柔らかくふわふわとしていますが、転圧を行うことで固く締まった路面となります。
その際注意が必要なのが温度管理です。アスファルトは高温で柔らかくなり、冷えると固まりますが、転圧の途中で冷えてしまうと歪みやひび割れの原因となります。
綺麗な舗装面に仕上げるためには、十分な温度を維持しながら転圧していく必要があります。
アスファルト舗装工事の施工で使われる専用車や道具と材料

アスファルトの舗装工事は専用の車両や重機、機材によって行われます。
ここでは、施工に使われる車体や道具を、材料と併せてご紹介していきます。
アスファルト舗装に使われる沢山の重機
舗装工事にはさまざまな建設機械や重機が用いられます。中にはアスファルトの舗装に特化した専用車両もあり、それぞれが担当する分野も多岐にわたります。一般的に使用される重機と、担当する作業工程についてご紹介いたします。
◆ブルドーザー
土や砕石を押し出すブレードを装着したトラクターで、関連業種でもよく見る地ならしを行うための車両です。路床や路盤の敷きならしに用いられます。
◆モーターグレーダ
大型車両の前輪と後輪の間にブレードと土壌を掻き起こす爪を装備した重機です。ブルドーザーに比べてより滑らかな整地が可能で、路床や路盤の仕上げに使用されます。
◆タイヤローラー
空気入りのタイヤを履いた車輪を多数取り付けた車両です。車両自体の重量を利用してタイヤで施工面を踏み締め、表層と基層の転圧を行います。
◆ロードローラー
タイヤではなく鉄製の車輪(ローラー)によって駆動する車両です。タイヤローラーよりも幅広の転圧が可能で、舗装表面も綺麗に仕上がるという利点があります。
アスファルト舗装に使われる様々な材料
舗装面を形成する材料についても解説していきます。主だって使用される材料は以下の通りです。
◆砂、砕石
舗装の土台を形成する路床や路盤に使用される材料です。砕石は下層路盤に用いられる大粒なものから、上層路盤に使われる小粒で均一な形状のものまであります。
◆アスファルト混合物
舗装に用いられるアスファルトは正式名称を『アスファルト混合物』または『アスファルト合材』と言い、正確にはアスファルトをつなぎとして配合した砕石や砂利などの混合物です。
骨材として配合されている砕石のほか、フィラーと呼ばれる鉱物性の微粉末と、石油から精製されたアスファルトを混ぜ合わせて舗装用の混合物が製造されます。
◆アスファルト乳剤
アスファルト混合物は加熱することで柔らかくなり、常温では硬質化します。
このアスファルトを常温でも液状で取り扱えるように処理したものがアスファルト乳剤です。アスファルトの微粒子を水に分散させたもので、混合物とは異なり乾燥することで硬化します。
この特性から高温のアスファルト混合物と路盤の砂利とを接着する用途や路面保護、水分の隔離などに用いられ、使用される箇所や使い方によってそれぞれ『プライムコート』、『タックコート』と呼び分けられます。
いずれもアスファルト舗装の品質を確保するうえで重要な材料です。
アスファルト舗装の施工で使われる道具
前述のアスファルト乳剤は、多層構造を持つアスファルト舗装の層同士の接着で主に使用されています。
乳剤の散布は専門の車両や手作業の道具を使用して行われており、使われる機材について一例を下記にご紹介いたします。
◆ディストリピュータ
アスファルト乳剤を充填したタンクとスプレー散布機構(スプレーバー)を備えたトラックです。散布口がバー状のため、均一にアスファルト乳剤を路面へ散布することができます。
またトラックが走行する速度によって、乳剤の散布量も調節が可能です。
◆スプレーヤー
手作業でアスファルト乳剤を散布するための道具です。
台車つきの乳剤タンクにポンプと散布ノズルが取り付けられていて、ノズルを手で持って散布していきます。
ポンプの動力はエンジンと手押しタイプがあり、いずれもピンポイントでの乳剤散布に適しています。
均一性という点ではディストリピュータが勝っていますが、スプレーヤーは小型なため狭い散布場所にも入り込むことができ、施工費用が安く、取り扱いの際も特殊な資格が必要ないという利点があります。
舗装で仕上げに使われるアスファルトフィニッシャとは
アスファルトフィニッシャとはアスファルト舗装工事の最終工程である基層と表層の敷きならし施工を行う重機のことです。
構造としては自走機能を備えたトラクター部に、加熱したアスファルト混合物を充填したホッパー、アスファルト混合物を舗装面に練り出して敷きならしを行うスクリードに分かれています。
ダンプトラックで運ばれてきたアスファルト混合物はまずホッパーに貯められ、施工に必要な分量を充填できたらそれをローラーでスクリードへ送り出し、パテをヘラで盛るように路面に敷いていきます。
スクリードの角度と幅を調整することで、地面に盛られるアスファルト混合物の厚みと幅の調節も可能です。
原則としてアスファルトは熱いうちに仕上げを行わなければならないため、大抵の場合はアスファルトフィニッシャの後をロードローラーやタイヤローラーが付いていって敷きならしたそばから転圧していくといった光景を目にすることになります。
アスファルト工事の品質管理方法
長年の使用を想定されているアスファルト舗装には、厳格な品質管理基準が設けられています。
アスファルト混合物は『練り物』であるため、混合時の温度や混ざり具合、転圧がしっかりできているかなど品質を決定するさまざまな要素が存在します。
同時に、それらは舗装面を外見から眺めただけでは判断しづらいものでもあります。
そこで、アスファルト舗装の施工の途中や施工後に品質を確認する試験を行い、これをパスすることで最終的な落成とすることができます。
以下の項で、アスファルト舗装工事に主に用いられる4種類の品質確認試験についてご解説いたします。
プルフローリング試験で路盤の不良をチェック
プルフローリング試験は、アスファルト混合物を敷き詰める前の、路盤が露出している段階で行う試験です。
締め固めた路盤の砕石の上で、荷重をかけたダンプトラックなどに走行させ、トラック通過後の路盤面に問題がないかを確認します。
試験は目視によって行われ、路床や路盤面に不良箇所を発見した場合は、その箇所に使用されている材料を一時撤去して良質な材料に置き換えるなどの改善処置を施す必要があります。
コア抜きでアスファルト量をチェック
コア抜きは、アスファルト混合物の敷き詰め施工が終わり、硬化が完了したあとに行う試験です。
仕上げの終わった舗装面上でランダムにポイントを決め、その場所にドリルで穴を開けて表層と基層に敷き詰められたアスファルト混合物の一部を抜き取ります。
抜き取ったサンプルから混合物に含まれる骨材が所定の粒度を満たしているか、つなぎのアスファルトは規定量が使われているか、転圧によってどの程程度締固められているかなどがわかります。
舗装の中でも最も風雨や荷重に晒され続ける表層と基層の品質をチェックする重要な試験です。
現場密度試験で路盤の締固め度をチェック
現場密度試験は路盤の仕上げが終わったあとに行われる品質試験です。
締固められた路盤に穴を開けて路盤材の一部を回収し、空いた穴に砂を詰めます。
これは砂置換法と呼ばれる工法で、どれだけ砂が入ったかによってまず体積を明らかにします。
回収した路盤材の重量を計り、先だって明らかになった体積で割ることで路盤材の密度を計算で導き出すことができます。
路盤がしっかり締め固められていれば規定の密度を満たしているはずなので、密度を計ることで路盤の締固め具合を確認できるという寸法です。
締固め具合は路盤の耐荷重性に直結し、締固めが不十分だと舗装面が上を走行する車の重量に耐えられる陥没するおそれがあります。
平坦性試験で道路の平坦性をチェック
平坦性試験は表層のアスファルト混合物の仕上げが完了した後に実施される試験です。3ⅿプロフィルメーターと呼ばれる手押し車のような平坦性測定器具を使用し、舗装面がきちんと平坦になっているかを確認します。
舗装面が平坦でないと、雨水が意図せぬ場所に滞留して水たまりになってしまったり、上を通行する人の負担になってしまったりするおそれがあります。
まとめ
アスファルト舗装工事の工程について、要点を下記にまとめます。
・アスファルトの舗装工事には大まかに分けて5つの工程がある
・重機や専用車両、液材散布器などさまざまな機材や道具が使用される
・舗装工事の品質管理には主に4つの試験が用いられ、それぞれ測定する要素が異なる
アスファルトは優秀な舗装素材ですが、デリケートな扱いが必要な材料でもあります。
特性を十分に発揮するためにどんな作業が必要かを把握することで、自分で工事業者に依頼する際にも打ち合わせをスムーズに進められるかもしれません。
今回ご紹介した知識が、少しでもみなさまのお役に立てれば幸いです。

代・
ラインを引き直したい
アスファルトの補修はオーバーレイ工法

アスファルトの工事には、オーバーレイ工法と呼ばれる手法があります。建築ではデザインコンクリートを使って床を石畳風に仕上げる手法もオーバーレイと呼ばれますが、今回ご紹介するのは舗装道路の工事で行われる工法です。
アスファルトは一度敷いた後の定期的なメンテナンスが必要な舗装材料なので、駐車場などをお持ちの方は、今後オーバーレイ舗装が必要になることもあるかもしれません。
駐車場などのコンクリート舗装地をお持ちの方は知っておいて損はない工法になりますので、ひとつひとつ見ていきましょう。
アスファルトのひび割れはオーバーレイ工法で修繕する
アスファルトが劣化したら、オーバーレイという工法で修繕します。
オーバーレイ工法とは、劣化したアスファルトの表面に新しいアスファルトを塗り重ねて道路舗装を復元するやり方です。どのような理由でどのような場所に施工されるのか、詳しく見ていきましょう。
オーバーレイ工法とは
オーバーレイ工法とは、すでに舗装されていたコンクリートが損傷したり、劣化したりした時に表面だけに重ねて舗装を行う工法です。
アスファルトはとても便利な舗装材料なのですが、耐摩擦性が低く、継続した負荷がかかるとすぐにへこんだり摩耗したりしてしまうという欠点があります。その害が起きる前に、使用状況によって5~10年のスパンで補修が必要になるのです。その時に行われるのが、表面だけを新しくするオーバーレイ舗装になります。
古いアスファルトと新しいアスファルトの間に乳剤という接着剤のようなものを撒くので、二つの間に空間ができてはがれてくるというようなことはありません。
オーバーレイ工法が行われる場所
オーバーレイ工法が行われるのは、地盤の沈下や路面の劣化が起こっている場所です。道路の表面に連続的に凸凹が起こり、平坦でなくなってしまった場合などにも使われます。
何度も施工を重ねてこれ以上オーバーレイができなくなった場合は、切削機で削り取ってから再舗装を行います。
トンネルの中など、交通量が特に多くできるだけ寿命を長く保たせたい場所には、砕石マスチックアスファルト舗装という方法でオーバーレイすることもあります。
アスファルトの上にコンクリートで舗装することも
オーバーレイ舗装ではふつう同じアスファルト混合物を上に重ねるのですが、時にはコンクリートを上に重ねることがあります。黒いアスファルトの上に白いコンクリートを載せるので、「ホワイトトッピング」と呼ばれます。アスファルト舗装で早くわだちが起こってしまう場所への抜本的な補修工法として発案されました。
1990年代はじめにアメリカで登場した試験舗装です。コンクリートは5~10㎝以上厚く敷きます。既存アスファルトを切削した後、表面処理を行うなどして切削面の清掃を行い、コンクリートを打設します。日本ではまだ一般的ではありませんが、2001年から埼玉県の県道などで試験舗装が実施されています。
オーバーレイ工法の流れ
オーバーレイ舗装の工事の流れは、具体的にはどのようなものなのでしょうか。
元々あるアスファルトの上に新しいアスファルトを敷くとなると一見単純な作業のように見えますが、注意すべきポイントはさまざまあるのです。使う重機や道路塗装ならではの注意点とともにご紹介します。
1.既存舗装版をチェック
既存舗装版が厚く、15㎝を越えてしまう場合は、コンクリート圧砕機か大型ブレーカーを使って舗装版を破砕します。コンクリート圧砕機も大型ブレーカーも、油圧ショベル機の先端に取り付けて使用します。圧砕機はハサミ型で、比較的軽量で小型のため狭い範囲で使いやすいです。
一方大型ブレーカーは打撃機で、それを先に取り付けたショベル機はコンクリート建造物の解体などにも使われます。
駐車場などの施工では、排水口などを設置したい場合はこの段階で溝を作っておきます。排水溝枡があるときはモルタルでかさ上げします。
2.路床と路盤を敷き均す
アスファルトの下地になる路床と路盤の整地を行います。地面は最下層から「路体」「路床」「下層路盤」「上層路盤」「基層」「表層」にわかれていて、普段自動車などは表層を走っていることになります。路床ははるか深くに存在し、道路の土台としてとても大切な部分です。
不陸の正整には、ブルドーザーやモーターグレーダーが良く使われます。
路床に使用されるのは主に砂です。敷き均しではマカダム、タイヤローラーを主に使って表面の転圧をします。
3.敷き均しと転圧作業
次に、アスファルト混合物を搬入します。アスファルト合剤を積み込み走行しながら式流しできるアスファルトフィニッシャーをいう建設機械で敷均しを行います。10tのロードローラーでアスファルトが熱いうちに踏み固めて安定させる初期転圧を行います。
そして、20tほどのタイヤローラーで二次転圧を行います。ニーディング(こね返し)作用によって、混合物の中にある粗骨材の配列を安定化し、丈夫なアスファルトを作ることができます。
目的によって変わるオーバーレイ工法

一口にオーバーレイ工法といっても、いくつか種類があります。「切削オーバーレイ」と「薄層アスファルト舗装」です。どちらも、表面のアスファルトが劣化してしまった(もしくはしてしまう)ことに対する対策なのですが、各工法には果たしてどのような違いがあるのでしょうか。
切削オーバーレイで高低差がでない舗装ができる
オーバーレイ工法との違いは、路面の高さを変えたくないときなどに、必要最低限の厚みだけを切削できることです。下地が荒れているときや沿道の建物との関係性から切削する可能性があるときに使われます。
道路の切削から舗装までを即日で仕上げることができるので、交通にも影響を与えにくい、アスファルトの速乾性が生きた工法になっています。
薄層アスファルト舗装で道路のひび割れが予防できる
薄層アスファルト舗装は、すでに作ってある舗装の上に、アスファルト混合物を厚さ2~3㎝の薄層にして舗装する方法です。完全にアスファルトが使えなくなってしまう前に予防として行われることが多い工法になります。
たわみ性や水密性、排水性など機能性を持ったアスファルト混合剤もあります。切削なしでできるうえ、使う材料も少ないので低コストな工法です。
まとめ
オーバーレイ工法のポイントについては以下の通りです。
● 劣化してひびが入るなどしたアスファルトの上に新しいアスファルトを塗り重ねる方法
● 地盤沈下や路面の劣化、連続的な凸凹が起こっている道路に使う
● 既存アスファルトの上にコンクリートを重ねる「ホワイトトッピング」という手法もある
● 既存舗装版を確認→路床・路盤を敷きならす→敷き均しと転圧の順番で施工
● 切削オーバーレイでは路面の高さを変えたくないときなどに有効
● アスファルトの劣化を食い止めるための安価な施工には、薄層アスファルト舗装
アスファルト自体は工事費が安く静音性も撥水性もあり、なおかつ工事後短時間で走行可能になるので、とても有用な特性を持っています。しかし、そんな便利なアスファルトにもへこんだり擦り減ったりしやすいという短所があり、定期的なメンテナンスが必要になります。
便利なアスファルトの欠点をフォローするのが、オーバーレイ工法という技術なのです。