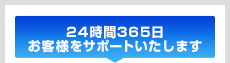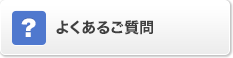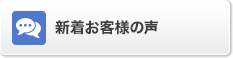作成者アーカイブ: administrator

代・
ラインを引き直したい
舗装に使うアスファルトの重量を計算する方法

一般的なアスファルトで舗装を行う場合、1立方メートルあたりの重量は2.5トン程度になると言われています。
ここでは、なぜその数字になるのかを計算過程からわかりやすくご説明し、実際の施工にあたってアスファルトの重量計算がしやすくなるよう役立つ知識をご紹介していきます。
またアスファルトには特性と使用用途によっていくつかの種類分けがされており、それぞれ単位あたりの重量も異なってきます。
舗装用のアスファルトにはどんなものがあるのか、その重量の計算式はどうなるのか、合わせてご解説いたします。
アスファルトの重量を計算する方法
アスファルトの重量を計算するにあたって、必要な数字が体積と比重です。アスファルト舗装の施工面積と厚さから体積を割出し、舗装に使用されるアスファルトの比重を掛けることで導き出すことができます。
ここでは、重量計算において前提となる基礎的な知識と、アスファルト特有の注意点についてご説明していきます。
比重について
『比重』とは、物体が同体積の水に対してどの程度重いかを示す言葉です。基準となる水の比重は1であり、1平方メートルあたりの重量が1トンと明確なため、体積に物体の比重を掛け合わせることで簡潔に重量を計算することができます。
比重は物体の『密度』によって求められます。密度は物体の体積あたりの重量を表す言葉で、密度が高いほど比重も高くなります。
アスファルトの重量を計算するうえでは、比重がとても重要になってきます。
体積から重さを求める計算方法
アスファルトの重量を計算で求める場合、体積と比重を掛け合わせる方法が使用できます。
体積は施工面積に舗装の厚さを掛けることで求められますが、通常アスファルトは敷き詰めたあとにロードローラーなどで踏み固めるため、若干厚みが目減りすることとなります。
これを『転圧減量』と言い、踏みしめられて減った分の体積を加味して計算する必要があります。踏み固められることで減少する体積はおよそ8%とされているため、転圧減量として1.08を計算式に掛け合わせます。
以上を踏まえたうえでアスファルトの重量計算を式に表すと以下の通りになります。
面積(m2)×厚さ(m)×比重×転圧減量(1.08)=重さ(t)
計算時の注意点
一般的に舗装に用いられるアスファルトは『密粒度アスファルト混合物』と呼ばれるものです。
比重は2.35とされていますが、実際に施工で使用するアスファルトは製品によって製造会社の定める比重が異なる場合があります。
事前にアスファルトの出荷プラントへ比重を質問して確認するようにしましょう。
また後述の通り使用するアスファルトの種類によっても比重は異なります。施工の際にどの種類のアスファルトを使うのかを確認しておくと計算がスムーズに行えます。
アスファルト混合物の密度

舗装に使われるいわゆる『アスファルト』は、正式にはアスファルト混合物と呼ばれ、密度によって種類分けがされています。
複数の種類があるアスファルト混合物は、それぞれ強度と重量が異なります。
アスファルト混合物の区別は配合されている粒子の大きさや密度(=粒度)によって決定され、強度順に『密粒度アスファルト混合物』、『細粒度アスファルト混合物』、『開粒度アスファルト混合物』などがあります。
舗装を行うにあたって求められるアスファルトの強度や性質は変わるため、必要強度に応じて使用する種類を選択しましょう。
アスファルト混合物の比率で種類が変わる
アスファルト混合物を構成する材料には以下のようなものがあります。
・『粗骨材』
目の大きさが5mmのふるいにかけた際に85%以上が残る、比較的大粒の砂利や砕石。
・『細骨材』
目の大きさが5mmのふるいにかけて85%が落下する、比較的小粒の砂利や砕石。
・『フィラー』
砂利や砕石を更に粉末状に砕いた鉱物質の微粉末。骨材同士の隙間を埋める役割を持つ。
・『アスファルト』
上記の骨材やフィラーをつなぎとしてまとめ、アスファルト混合物として完成させる接着剤。石油からガソリンや重油などを分離して精製する。アスファルトの代わりにセメントをつなぎに用いるとコンクリートになる。
これらをどのような比率で混合するかによって、前項で紹介したような各種類へと分岐していきます。
上記材料はそれぞれ比重が異なるため、配合割合によってアスファルト混合物自体の比重も変わってきます。
各アスファルト混合物について、特徴と用途を下記に解説いたします。
◆密粒度アスファルト混合物
日常生活で最も見かけることの多いアスファルト舗装で、道路の舗装によく使用されています。大きな粒が混じっているのが特徴で、安価かつ短期間で施工が可能という利点があります。
変形しづらく、摩耗に強く、滑り止め効果が高いというのも重要な特性です。
◆細粒度アスファルト混合物
密粒度のものより小さな粒を多く混合した舗装です。粒子が細かく隙間が小さいため、耐水性が高くひび割れにも強いという特徴を持っています。
◆開粒度アスファルト混合物
小さな粒を低密度に分布させた舗装です。表面が上記二つを比較しても非常に粗いのが特徴で、水をよく吸うため水たまりが出来にくいとされています。
また表面に水分が滞留するのを防ぐため、路面がスリップしにくいという特性も備えています。
アスファルト混合物の比重と性能の違い
一般的なアスファルト混合物の、それぞれの比重と性能、使用されるシーンについて以下にまとめます。
◆密粒度アスファルト混合物
比重:2.35 性能:最も普及している舗装用アスファルト。 頑丈で滑りに強く、施工が安価。
主に使用される場所:全国の国道を始めとした人通りの多い道路。急こう配のある部分。
◆細粒度アスファルト混合物
比重:2.30 水に強くひび割れが起きにくい。一方で変形しやすい難点がある。
主に使用される場所:大型トラックなどの重量貨物車が頻繁に運行する場所や駐車場。
◆開粒度アスファルト混合物
比重:1.94 水はけが良く、路面が乾きやすいためスリップしにくい。反面耐摩耗性では上記に劣る。
主に使用される場所:冠水しやすい場所や雪国など、路面が濡れた状態になりやすい場所。
アスファルトの単位重量
比重がわかれば、体積あたりの重量を計算で求めることが可能です。下記は、各アスファルト混合物の1立方メートルあたりの重量になります。
・密粒度アスファルト混合物 約2.5t
・細粒度アスファルト混合物 約2.4t
・開粒度アスファルト混合物 約2.0t
上記の単位重量は、あくまでも一般的な比重とされている数字を掛け合わせたものです。
前述の通り、舗装用のアスファルト混合物は製造しているメーカーによって比重が異なる場合がありますので、施工の前にあらかじめ製造プラントや専門家へ話を聞いておくことをおすすめします。
まとめ
アスファルトの重量計算について、以下に要点をまとめます。
・重量を割り出す計算式は、面積×厚さ×比重×転圧減量=重量
・比重はアスファルト混合物のメーカーによって異なる場合があるため、事前の確認が必要
・舗装用アスファルト混合物には種類があり、それぞれ強度と特性、比重が異なる
アスファルトは舗装目的や周辺環境によって使用する種類が変わってきます。重要事項を確認し、適切な施工にお役立てください。

代・
ラインを引き直したい
コンクリートやアスファルトの撤去手順・費用相場|撤去時の工法

建物の解体工事などで発生するブロック塀などの不要なアスファルトやコンクリートを撤去するときの手順はご存じですか?撤去工事にはいくつかの種類があり、それぞれでかかる費用が異なります。また撤去をするさいに、済ませなければならない手順もいくつか存在します。
そこで今回は、アスファルトやコンクリートの撤去をおこなう工事の種類や手続きなどの撤去工事のおもな流れなどをご紹介します。この記事を読んで、アスファルトの撤去工事についての知識を手に入れてましょう。
目次
解体工事のおもな流れ
まずは、不要なアスファルトなどが発生する解体工事をおこなうさいの、おおまかな流れをご紹介していきます。
1.解体工事の現地調査・お見積り
最初は、解体工事をおこなう場所の調査をおこなう必要があります。この調査で、解体する建物の種類や実際に作業をおこなう場所やその近隣の環境、搬入搬出をおこなうためのルートなどを確認していきます。
そして、その確認した情報をもとに、解体作業をおこなうために使用する重機車両などを選択していきます。その情報をもとに、解体工事にかかる費用の見積もりを出します。そして実際にどのような解体方法で工事をするのかなどを業者に説明してもらいます。
2.届け出の提出・手続きなどを行う
解体工事の契約を業者とおこなったあとは、解体する建物の規模が80平方メートルを超える場合に建築リサイクル法の定めにより市区町村に届出をする必要があります。この届出から大体1~2週間後から解体工事をおこなうことが可能の場合が多いですが、市区町村により異なりますので、確認するようにしておきましょう。
3.周囲の方へのあいさつ
業者との契約や役所への手続きをおこないましたら、ついに工事に着手するのですが、その前に工事現場の周囲の人達へのあいさつをおこないます。そのさいに、おこなわれる解体工事の概要や工程、そして緊急時の連絡先も伝えておきます。
4.工事に着手する
工事前のあいさつも済み、ついに工事に着手します。解体工事の期間中はその環境に合わせて、防音や振動、安全対策などを徹底するようにしましょう。
5.工事をしたときに発生した廃材の運搬
解体工事をおこなうと、さまざまな廃材が発生します。そうした廃材は分別をおこなったのちに、処理施設へと搬送してもらいます。その搬送される廃材の中には、アスファルトやコンクリートなどの産業廃棄物が存在しています。
これら産業廃棄物は、処理施設で再資源化のための処理をおこない骨材などに再利用されます。
6.現場確認
最後に解体工事が完了したあとに、現場確認をおこないます。この確認で特に問題がなければ解体工事は終了ということになります。
アスファルトの撤去・補修工事の費用相場

ここからは、解体工事などで発生するアスファルトの撤去及び補修工事の費用についてご説明していきます。アスファルトの撤去及び補修の費用は、そのアスファルトの厚みや補修する広さ土地の広さなどで価格が変化します。
また、撤去及び補修は基本的に重機を使用しておこないますが、その使用する重機によっても価格はことなってきます。そこで、使用する重機が違う2つの工法について説明していきます。
IH式工法
IH式工法は電磁誘導加熱を使用してアスファルトで舗装されている部分を加熱することで、アスファルトの接着を解き、アスファルトの撤去を簡単におこなう方法です。この工法でアスファルトを撤去するさいに騒音や振動といったものの発生しづらいという特性があります。
また、アスファルト下の鋼床版に傷をつけることなく、アスファルト撤去をおこなうことができるという利点もあります。しかし、特殊な重機を使用するという点や日数がかかることもあり費用が高くなることもあります。
オーバーレイ工法
アスファルトを一部だけ剥がしたあとに、上から新しいアスファルトを重ねていく手法のことを、オーバーレイ工法といいます。この工法は、作業時間が少なく済むことから、IH式工法に比べると費用が安価になりやすいです。
また、工事の期間そのものも短く済むため、近隣住民への影響も少ないという利点があります。
コンクリートの撤去工法と費用相場
アスファルトと同様に、撤去するコンクリートの厚さや総面積によって費用に違いが出てきます。また、コンクリートの撤去もいくつかの工法が存在しています。
クラッシャー工法
ダイヤモンドカッターを使用して、コンクリートを削っていく工法です。別名ワイヤーソー工法とも呼ばれ、ブロック塀やコンクリート壁の撤去などに適しています。比較的作業音が静かで、場所を選ばないという点が魅力です。
ウォールソー工法
切断するコンクリートに予定切断線を引き、その線に沿って走行レールを設置します。そのあとレールに切断機を取付けて、レールの上を移動させながらコンクリートを切断していく工法です。高い切断制度が要求される、建物の改修や耐震工事などで特に使用されることが多いです。
ウォータージェット工法
超高圧水を利用することで、コンクリートを無振動で削り取るように除去していく工法です。特に老朽化したコンクリートなどを部分除去するさいなどに使用さえることが多いです。昔は、低圧で水量が大きいタンクの機械が主流でしたが、最近では高圧で少ない水量での施工も可能になっているため、環境性などの改善がみられています。
圧搾工法
圧搾機を使って、コンクリートを圧で砕きながら破壊していく工法です。粉塵などが発生しやすい工法ですが、音が比較的小さいというメリットがあります。
新たに同じ素材を施工し直すのならば、補修するのもアリ
ヒビが入ったりめくれてしまっているコンクリートを撤去してから、再度コンクリートを引き直す場合は、同じコンクリート素材を使って補修をおこなうのも1つの手段です。補修工事は、一般家庭の駐車場などのように、1日に何回か車が通過する程度であれば十分な耐久性を得ることができます。
ただし、大型施設などのように、コンクリートに高い耐久性が必要な場合には向かない方法でもあります。
解体工事を行うときに気をつけたいこと

実際に解体工事をおこなっていく場合に、いくつか気をつけておきたいことがあります。ここではそれを紹介していきます。
業者選びに気をつける
解体をおこなってくれる工事業者の選ぶさいには2点ほど気をつけなくてはいけないことがあります。
ひとつは、発生した廃材などの産業廃棄物の処理を法律に沿って正しく処理してくれる業者かどうかという点です。産業廃棄物の取り扱いは法律によって厳しく定められています。そのため、そうした部分の扱いを間違っていると、依頼した側にも責任が出てくる可能性がありますので、その点はしっかりと確認をとるようにしてください。
もうひとつは、費用が高額になりやすい作業のため、業者ごとの金額の振れ幅も大きくなりやすいという点です。頼む側としては、当然ながら費用が安く済む業者に依頼したいです。そのため、実際に依頼する前にいくつかの業者から見積もりをとり、内容を比較して選ぶことをおすすめします。
周囲へのあいさつは必ずおこなう
工事を始めるさいには、その現場の周囲への挨拶を必ずおこなうようにしましょう。解体工事は騒音や振動、粉塵などがすくなからず発生します。それに、搬入や搬出といった作業から大型車両の出入りも頻繁になりやすいため、そうしたことが近隣の迷惑に繋がりやすいです。
そのため、工事を始めるまえに、ご迷惑になる可能性もあることや、もしも問題がある場合の連絡先なども伝えておくことがトラブルを未然に防ぐための方法といえます。
駐車場を解体するときに合わせて気を付けたいこと
駐車場を解体するさいに気を付けておきたいことがいくつかあります。まずは、その駐車場がある土地に以前建物が建っていなかったかを確認するようにしてください。住宅跡地などに駐車場が作られた場合、建物さえ無くなってしまえばよいことから、当時の解体工事が簡単なものであった可能性があります。
そうした解体工事のあとにできた駐車場だと、ガス管や水道管、浄化槽などがコンクリートの下に埋没している可能性が高いです。その他、建物の基礎部分や土間コンクリートなどが残っている可能性もあるため、前もって調べておくことをおすすめします。
また、その土地がもともと埋め立て地だった可能性もあります。その場合、地中に大量のガレキが埋まっている場合があるため、それらの除去及び廃棄をおこなう必要があります。このように、さまざまな昔の工事の跡が残っている可能性があるため、事前に調べておくようにしておくと安心です。
まとめ
アスファルトやコンクリートの撤去手順などについて知ることができたでしょうか?撤去工事をおこなう場合は、現地調査や各種手続き、現場周囲への挨拶などが必要になります。また、工事をおこなうことで発生する廃材の中には、多くの産業廃棄物が含まれます。
それらは法律で定められた正しい処理をおこなう必要があるのも忘れないようにしてください。そのため、依頼する業者には、これらの部分をしっかりと対応・確認してくれるかを調べるようにしておきましょう。
そして、こうした工事の費用は、撤去及び補修をおこなうさいのアスファルトやコンクリートの厚さや総面積などが料金に関わってきます。そのため、一概に撤去費用がいくらかと簡単に調べることはできません。
業者のほうで調査及び見積りを出してもらうことで確認するようにしましょう。その他、駐車場を解体する場合は、地面にガス管や建物の基礎部分、土間コンクリートなどが埋まっていることもあるため、確認するようにしましょう。

代・
ラインを引き直したい
アスファルト舗装で駐車場を作る手順と作業工程

駐車場を作るときによく使われるのがアスファルトです。アスファルトの駐車場はどのように作られるのでしょうか。
アスファルトを使った駐車場の舗装工事は、大きく分けて4つの工程を経て完成されます。地盤作りからアスファルトを締め固めるまでの工程をわかりやすくご紹介します。
地盤が弱い場所でもアスファルト舗装をできる場合があります。例えば田んぼや畑など、アスファルトにできないのではないかと思われる弱い地盤でも、砂利を敷くことによって強度を得ることができ、アスファルト舗装で駐車場を作ることができるのです。しかし、地盤の弱い場所では注意点もありますので、アスファルト舗装を考えている方は、気を付けるべきポイントについても確認しましょう。
本記事ではアスファルト舗装について、コンクリート舗装との違いにも触れながらご説明いたします。
目次
駐車場を作るときの作業工程
具体的な舗装工事の工程について種類ごとに説明する。代表的な舗装工事としてアスファルトを重点的に紹介する。
地面の舗装工事で一番使用されるのがアスファルトです。本記事では、複数ある舗装の中でも一般的な舗装方法であるアスファルト舗装についてご紹介したいと思います。
アスファルト舗装の工程は大きく4つに分かれます。どのような方法でアスファルトが地面として完成するのか、手順を見ていきましょう。
手順1:掘削
はじめに、掘削という作業をします。この作業はアスファルト舗装における下準備の段階です。ショベルカーを使用し、土を掘削して不要な土を取り除きます。
駐車場を作りたい場合などには、道路と駐車場の間に段差ができることがないよう、アスファルトの厚さなどを計算し、地面を適当な深さまで掘り下げます。
手順2:路盤の整正
アスファルトを敷く前に、砕石と呼ばれる粒状の材料を掘削した地面に敷きならし、路盤を整正します。
この砕石を敷く段階での出来の良さが、アスファルト舗装が完了したときの見栄えや強度に大きく影響を与えます。丁寧に行うべき作業です。
手順3:アスファルトの敷き均し
ここでやっとアスファルトの登場です。アスファルト混合物を整正した路盤の表層に敷きならします。
小さい面積の舗装の場合はレイキという道具を使って人の手で敷きならします。大規模な舗装をする場合にはレイキを使うほかに、フィニッシャーという重機でアスファルト混合物を敷きます。フィニッシャーで敷きならすことで、広い面積でも美しい仕上がりにすることができます。
手順4:アスファルトの転圧
最後に転圧作業をします。120度程度の熱さのアスファルトを転圧機械で上から圧縮することで、締固めます。アスファルトの表面温度が約50度まで冷めれば使用することができます。50度以上の状態で車止めをしたり足を踏み入れると、アスファルトが変形しひび割れなど劣化の原因になりますので、時間を置くことを忘れないようにしましょう。
弱い地盤の上で駐車場工事するときの注意点

畑などの地盤が弱い土地をアスファルトの駐車場に変えるときには、通常とは施工の方法が異なります。それは、地盤を強化する必要があるからです。
弱い地盤でもアスファルト舗装をすることは可能ですが、舗装が劣化しやすくなるだけでなく、思わぬ事故が起こる危険性もあるため、地盤が十分な硬さを持っていないことで起こり得ることを想定して舗装工事を行わなければなりません。地盤が弱い場所を舗装する場合に気を付けるべき3つのポイントを見ていきましょう。
初めに地盤改良を行う
田んぼ、畑では雑草がぼうぼうと生い茂っていることが少なくありません。雑草はどこにだって生えてしまうものですが、田んぼや畑の土は栄養があるため、より草が生えやすいのです。
雑草が生えやすい状態のままアスファルト舗装をすると、アスファルトが劣化しやすくなるほか、舗装をして数年後にアスファルトの隙間から草が生えてくるなんてこともあります。できるだけ安全で美しい舗装を保つためには、草が生えにくい下地にしてから舗装をする必要があります。
強い地盤にするには、セメント材を用いた地盤改良工事をします。基盤工事をしっかりとしておくことで雑草が生えにくくなる効果があるので、畑や田んぼだった土地ならぜひやっておきたい工事です。
砂利の敷き均しで排水性を得る
地盤強化をした後には、砂利を敷き均すことも大切です。砂利をコンクリートと弱い地盤の間に挟むことで強度を高めると同時に排水性を高めます。砂利・砕石を地盤の上に敷いて均したあと、ローラーで転圧します。10センチ程度の砂利を敷くのが一般的ですが、元々地盤に排水性がある場合には薄めの砂利を、排水性がない土地では厚めの砂利を敷くというように、砂利の高さは土地の状況によって調節されます。
砂利に関しては、コストも考える必要があります。砂利の密度や種類はさまざまで、それぞれの強度や性能が異なります。業者に舗装工事を依頼する際には、排水性を意識しつつ、予算に合う種類の砂利を提案してもらいましょう。しかし、基本的に地盤が弱い畑や田んぼでのアスファルト舗装は費用が高くなりやすいということは頭に入れておきましょう。
必要な砂利の層の厚さに達していないとどうなる
先ほど砂利は高さ10㎝前後で、排水性の高さによって調節をすると述べましたが、砂利の厚さが足りないとどのようなことが起こるのでしょうか。
水を取り除くことのできないアスファルトは劣化のスピードが速くなります。小さなヒビが徐々に大きくなり、アスファルトに穴が空いてしまうこともあるようです。穴が空いてしまうと再舗装するのにもまたお金がかかってしまいます。コストを気にしすぎてアスファルトが劣化しやすくなるようなことにならないように、排水性を意識して基盤工事はしっかりと行うことが大切です。
駐車場の舗装はアスファルトがおすすめ

舗装用の素材としては、アスファルトのほかにコンクリートも広く使用されています。駐車場を創るためには、どちらの舗装が良いのでしょうか。
ここでは、アスファルトを駐車場舗装に選ぶと得られるメリットをご紹介します。
駐車場舗装は種類が豊富です
駐車場舗装にはさまざまなデザインがあります。特に、カラーバリエーションが豊富でデザイン性の高いコンクリートでの舗装を職人際に依頼すれば、おしゃれで見栄えのよい駐車場にすることができます。例えば、薄い色のコンクリートを使用すれば柔らかい印象を演出することができますし、ブロックタイルや芝生などと組み合わせることで、他の住宅とは違う、自分なりの個性を表現することができます。
アスファルトは黒やダークグレーな印象ですが、赤茶をはじめとした、目立つ色合いのカラーアスファルトも使用されています。コンクリートの他には、砂利やタイルを取り入れれば、一味違った特徴的な駐車場になります。
駐車場舗装はアスファルトがおすすめ
コンクリートに比べデザイン性に劣るアスファルトですが、カラーアスファルト舗装をすれば、着色された駐車場を創ることができます。
・舗装工事後すぐに使用できる
アスファルトの強みは何といっても、硬化の速さです。コンクリート舗装後には使用するためには数日待たなければなりませんが、アスファルトならその日のうちに使い始めることが可能です。急いで駐車場を創りたい方にはぴったりな舗装だといえます。
・走行性の良さと快適さ
やはり、アスファルトは地味にはなりますが、もともと走行性が良い上、デザインを施すこともあまりないので、使い心地が非常に良いです。
・メンテナンス含めても施工費用が安い
材料の価格が安いアスファルトは、工事も安く済みます。また、デザイン性を高くすることが難しいため、デザインに凝って費用が高くなってしまう、ということも少なくなるでしょう。
まとめ
今回は、駐車場工事の手順と、地盤が弱い場所での舗装工事の注意点、そしてアスファルトを採用する利点をご紹介しました。
● アスファルト舗装の手順は、掘削→路盤補正→敷き均し→転圧
● 畑や田んぼは草が生えやすく地盤が弱い
● 地盤の強化には、セメント材を用いて地盤改良が有効
● 砂利の厚さに注意し、排水性を高めることが大切
● デザイン性には劣るが、施工費用や硬化のスピードがアスファルト舗装のメリット
これらの事に注目して、駐車場を舗装してみてください。